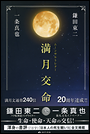ニューカマー宗教の日本における展開(2/2ページ)
大阪国際大教授 三木英氏
ニューカマー仏教の伸張も著しい。たとえば台湾仏教である。台湾には五大仏教と称される教団が存在するが、そのうちの中台山と佛光山が国内に寺院を建立している。2018年には後者の日本総本山が群馬・伊香保に完成したばかりである。寺には台湾出身者ばかりでなく、人民共和国出身者も足を運ぶ。女性信者の多いところが特徴といえる。
ベトナム仏教寺院建立が近年相次いでいることも、注目に値する。その大半は、ベトナム戦争終結後の1970年代末から日本に定住するベトナム人たちが、仕事の合間に手弁当で、協力し合って整備してきたものである。筆者はこれまで、六つを訪問してきた。在留ベトナム人口の急増している昨今、寺の数はさらに増えていよう。ベトナム出身者は自分たちの寺に集まって本尊に祈り、仏教を学ぶ。また寺は、日本生まれの若い世代にベトナム語・ベトナム文化を伝える場でもある。
上座仏教の進出にも言及しよう。タイ仏教の寺院は既に10カ寺を優に超えた。スリランカ人僧侶が住職を務める寺も、筆者の確認する限り、七つある。それらの寺院に参集するのはタイやスリランカの出身者がほとんどであるが、日本人信者の姿も散見される。“満たされない思い”で彷徨して上座仏教にたどり着き、いま仏教研究で充実した日々を送っているとは、スリランカ寺院で出会った日本人男性から聞かされたことである。
なお上座仏教といえば、日本テーラワーダ仏教協会が、その活発な出版・講演活動によって広く知られているだろう。その活動に参与しているのは大半が日本人である。この点において、すべてのニューカマー宗教のなかで当協会が異色であることは、附記しておきたい。
増加を続けるニューカマーであるが、彼らについて日本人が知るところはまだ少ない。『顔の見えない定住化』とは、日系ブラジル人の調査を行った日本人社会学者による研究書のタイトルであるが、日本人との接触機会に乏しい(よって顔が見えない)状況は、日系人に限らず、他のニューカマーにも該当していると判断できる。まして独自の宗教施設に集うニューカマーの存在は、「宗教への無関心」を標榜する日本人の大多数にとり、なお遠い。
とはいえ時がたてば、来日して働く外国人はさらに増え、ニューカマー第二世代が成長する。ニューカマーと日本人が顔を見合う機会は、コンビニ以外に、地域・学校・職場でも着実に拡大して二者の関係には変化が生じてくるだろう。こうした動向は、日本宗教にも波及するのではないか。
いま国内カトリック教会のミサには高齢の日本人信徒と並んで多数の外国出身者が参列している。神道・仏教・キリスト教の代表者が出席して異文化交流について論じ合う会議が某イスラーム団体のマスジドで毎年開催されている。在日ベトナム人が営む法要のため、住職が自坊を会場として提供するというケースもあった。これらの事例は、日本宗教の未来の一端を示唆しているかもしれない。
いま日本人の生活と密接に関わる仏教も、渡来してきた6世紀には、ニューカマー宗教であった。それが人々に受容され、日本文化の根底をなすほどに浸透していったものである。キリスト教も16世紀のニューカマー宗教で、禁教後に潜伏したキリスト教は独特な「隠れ」の文化を形成していった。そしてキリスト教は19世紀に再来し、現代日本の文化・教育・医療等の分野で存在感を発揮している。
20世紀末以降、日本は海外からの宗教の進出を経験するようになった。それは日本にとって、初めての経験ではない。今回のニューカマー宗教は日本における人と社会に、そして日本宗教に対して、どんなインパクトを与えていくのか。筆者は研究者として、それを見極めることが、自身の責務であると考えている。