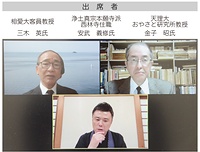目には見えない時間 “準備”が生の舞台に結晶(6月27日付)
効率や決まり切った尺度によらずに物事を極め、またよく見るということについて、京都の能楽師・有松遼一氏の著書『舞台のかすみが晴れるころ』が示唆深い。表現する・演じるということと、それを観る・感じ取るということについて華道や他の芸との共通性も踏まえて書いた「目には見えないもの」という一節が大学入試問題に採用され注目されている。
有松氏は、花をありのまま「立てる」花士を名乗る華道家・珠寳氏の「花を生ける前にほとんどのことが終わっている」との弁を引いて、他の芸事でもその表現に至るまでのこと、つまり「表面に表れる時間だけでなく見えない水面下のはたらきも勘定に入れ」「さまざまな準備、訓練、心づくしに接」することの重要性を強調する。
この道理は人生全般に通じ、行為と成果の価値を時間や金銭の多寡で測ることの無意味さを示した上で、自らの能では、「舞台はなまもので、その場の気韻からさまざまな要因が出来して結晶になる」と述べ、そのような目に見えない“風”のようなものを感取し表現する術を教わるのが稽古であって、映像を見て型をまねて芸をつくるだけでは内実を伴わないとも話している。
見える部分というのは、分かりやすくもあり、誤りやすいのだ。そしてまた、その芸を観る側も、「本物」を味わって自分なりの豊かな感性を持つことが大事で、自らの目や舌に自信がないと、目前に観ている舞台そのものに対峙せず、蘊蓄や周縁の知識に寄りかかって楽屋落ちの裏話に終始しがちだという。音楽や美術などアートや料理の味についてもよく指摘されることだが、的を射ている。
これは宗教者の姿勢にも両面で当てはまるだろう。いのちを尊ぶ、人を支えるという教えは決して抽象的ではなく、現実の世の中の場=舞台でこそ実現されるべきものである。そのためには普段からの社会の諸課題への目配りという「稽古」が前提であり、それは型通りの基準による見方ではなく深いものであるべきだ。
そしてその日常の訓練の発露は、通り一遍のお話や身内にだけ通じる専門用語による論評ではなく、その教えが求める行為であり、「なまもの」たる舞台、つまり世間の個々の事象に即した個別一回性の行いとなるだろう。
極めて宗教的な「祈り」を例に取っても、平素から人々の苦難に無関心な宗教者が例えば災害現場でただ祈る姿だけを見せても、「一体、誰のためなのか」と、実際に被災者に寄り添う僧侶や牧師らからは疑問が投げられるのだ。