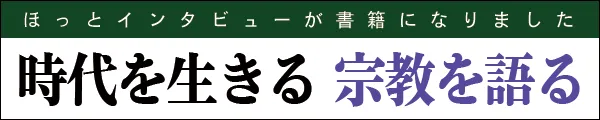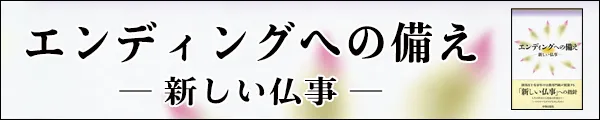明治期の真宗大谷派婦人法話会 ― 仏教教団と女性の国民化(1/2ページ)
大阪大谷大文学部教授 岩田真美氏
近代の本願寺教団は、他の仏教教団に比して婦人会運動が活発であったといわれている。
まず真宗大谷派の婦人会運動としては1886(明治19)年、東京の浅草別院(浅草本願寺)に「貴婦人会」が創設された。発起人は東本願寺第22代法主となる大谷光瑩であった。会長には三条治子(内大臣・三条実美の妻)が就任しており、東京在住の上流階級婦人を集めて法話会を行っていた。光瑩は72(明治5)年から翌年にかけてヨーロッパの宗教事情を視察し、早くから女性教化の必要性を認識していたようである。
本願寺派においても88(明治21)年には、西本願寺第21代法主の大谷光尊、洋行を経験した島地黙雷らが中心となり、築地別院(築地本願寺)に「令女教会」を発足させている。初代会長には毛利安子(元長州藩主・毛利元徳の妻)が就任しており、東西両本願寺の仏教婦人会は「貴婦人」「令女」を集めて講話を行う教化団体としてはじまった。86年には世界女性キリスト者禁酒同盟(WWCTU)のメリー・レビットが来日しており、多くの女性を集めて各地で講演を行ったことで、東京の日本橋教会に「東京婦人矯風会」が発足している。東西両本願寺の動きは、キリスト教が上流階級婦人の教化活動に成功していたことへの対抗でもあったと考えられる。
こうした上流階級中心の婦人会運動が、大衆化していく契機となったのは日露戦争後のことである。すでに大谷派では90(明治23)年に京都の東本願寺に「婦人法話会」が創設されており、当初は本山役員や旧家臣の妻らを集めて法話会を行っていた。それが1904(明治37)年には趣意書と会則を定め、京都に本部を設けて活動を拡大させ、銃後支援に取り組むようになっていく。
趣意書には「国の基は家にあり、家の禍福多くは婦人の心による。世の婦人克く其徳を修めて、清き光ある家庭を為さば、国民の心自ら高く潔よく、社会の幸福此に現れむ。されど其心常に大悲の光に触れて、外に仁慈清浄の美徳を表すにあらずば、世の婦人女子、何によつてか其心を修め其家を斉へむや。本会の目的正に此に在り。」(『真宗大谷派婦人法話会五十年史要』1941年、21㌻)とある。ここでは「国の基は家」にあることが示されている。仏教の教化によって、婦人が「家庭」をおさめることは国家や社会の幸福につながるとされ、女性の「国民化」が意識されていたことがわかる。
この「家庭」という語は1880年代後半(明治20年代)以降に広く使われるようになる新しい言葉である。近代の資本主義経済の発展は「女性は家庭(私領域)」「男性は仕事(公領域)」という性別役割分業を生み出すことになるが、それは日本の近代化によって広がった新たな思想や規範でもあった。同じく1904年には本願寺派でも、西本願寺に仏教婦人会の本部が置かれ、各地に支部が置かれる形で婦人団体の組織化が本格的に進んでいく。東西両本願寺の婦人会運動は、日露戦争の銃後の軍事支援を契機として活動の場を広げていくことになる。これらの背景には、01(明治34)年に創設された「愛国婦人会」の存在が関係していたのではないかと筆者は考えている。
「愛国婦人会」の創設を主唱したのは大谷派寺院出身の奥村五百子であった。兄の奥村円心は大谷派の命で朝鮮布教に従事した僧侶であり、その影響で五百子は朝鮮に渡り、1898(明治31)年には光州に実業学校を創設している。そして北清事変(義和団の乱、1900年)に際し、大谷派から慰問使として派遣された連枝の大谷勝信、南条文雄らに合流し、戦地の惨状を視察したことが、「愛国婦人会」を創設するきっかけとなった。帰国した五百子は、後に大谷派23代法主となる大谷光演をはじめ、政治家の近衛篤麿、軍人の小笠原長生、教育者の下田歌子や山脇房子らの協力を得て、創設に向けた会合を重ねていた(『愛国婦人会の起源』愛国婦人叢書第1号、1932年、6㌻)。