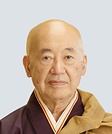四国の文化を世界に発信する「四国遍路」(1/2ページ)
愛媛大教授 胡光氏
2015年1月、ニューヨーク・タイムズ紙ホームページで、その年訪れるべき世界の52カ所が発表され、日本で唯一「四国」が選ばれて、「四国遍路の場所」として紹介された。以来、外国人遍路の姿は確実に増えている。彼らは必ず、遍路の白装束を着て歩いて遍路をする。彼らが日本の中で四国を選ぶのは、「ロスト・ジャパン」すなわち、失われた日本の自然や文化を四国の中に求めることが多く、遍路をした後の感想では、四国の自然や人々(「お接待」)への称賛が加わる。私自身も彼らを案内した時には、同様の答えが返ってきた。
ニューヨーク・タイムズは、四国遍路に1200年の歴史があり、特に松山は札所が集中する重要な場所であるとともに、120年前に建てられた楼閣のような日本最古の温泉があると特筆している。この文章には四国遍路や道後温泉の特徴が凝縮されている。本館が完成したのは、明治時代の1894年、日清戦争の年であり、まさに司馬遼太郎が描く『坂の上の雲』の時代である。翌年、松山中学に赴任した英語教師・夏目漱石は、後に『坊っちゃん』を著し「ほかの所は何を見ても東京の足元にも及ばないが温泉だけは立派なものだ」と完成直後の道後温泉の雄姿を記している。現在、道後温泉でお遍路さんの姿を見かけることはないが、本館完成以前には全てのお遍路さんが訪れた場所であり、四国遍路と道後温泉を合わせて紹介したニューヨーク・タイムズの記事は故なしとしない。
世界遺産がない四国では、四県と関係市町、経済界、霊場会、大学、ボランティア団体など産官学オール四国体制で世界遺産推進協議会を組織して、世界遺産化を進めており、愛媛大学でも四国遍路・世界の巡礼研究センターが協力協定を結び、学術面から支援している。小稿では、世界遺産化のために必要とされる「顕著な普遍的価値」を、四国遍路の歴史の中から探ってみたい。
四国遍路は、徳島・高知・愛媛・香川の四県からなる、四国一円に広がる弘法大師空海ゆかりの八十八箇所霊場を巡る全長1400㌔㍍に及ぶ壮大な回遊型巡礼である。四国遍路の原型は、1200年以上前に空海が行ったような、四国の自然と同化しようとする山林修行であった。讃岐出身の空海自身が記した出家宣言書『三教指帰』には、阿波大瀧嶽・土佐室戸崎・伊予石鎚山などでの厳しい修行の様子が詳しい。平安時代には、都から離れた山海の難所を回遊する「辺地修行」へと展開して、多くの僧が四国へ渡ってきた。石鎚山等の山岳信仰、浄土への入り口としての土佐室戸岬等、都から南西に位置する四国は聖なる島としての信仰が篤かった。平安時代末(12世紀)に著された『今昔物語』『梁塵秘抄』には、僧が衣を濡らして修行する「四国の辺地」の語が見える。「辺地修行」ならびに「四国」を記す最古の例が同時に現れることは、聖地四国を象徴するものである。
四国に生まれ、四国で悟りを開いた空海は、唐で密教を学び、大日如来や不動明王など新たな仏と、曼荼羅など難解な教義を可視化するシステムを伝え、仏教の世界観を日本に広めた。さらに、医学・土木・文学・教育など多方面での活躍が国民的な信仰を誕生させた。
没後86年に醍醐天皇から弘法大師の尊号を賜り、高野山奥之院で永遠の瞑想を続ける大師として尊崇を集めるようになると(入定信仰)、鎌倉時代には大師の遺跡を巡る修行が始まり、「四国辺路」と呼ばれる巡礼としての形を整えてくる。弘法大師が「四国辺路」開創に関わったことを記す最古の史料は、道後石手寺の由緒を記した室町時代・1567年の「刻板」である。これによれば、衛門三郎という富豪が私欲を肥やし仏神を信じないため、8人の男子が死に、自ら剃髪して四国辺路を行った。阿波焼山寺で病死する時、伊予国司になることを望み、空海(弘法大師)は八塚右衛門三郎と書いた石を握らせる。後に河野家でこの石を握った男子が誕生し、ゆかりの安養寺に奉納して、石手寺と改称したという。四国遍路開創を伝えるだけでなく、「死と再生」という四国遍路の重要なモチーフを示している。