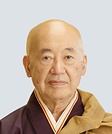オウム後継団体の現在―地下鉄サリン事件から25年④(1/2ページ)
ひかりの輪脱会者友の会 中山尚氏
「オウム真理教入信の年に結婚し1女1男に恵まれた。職を転々としながら活動したが、オウムに反対し続けた妻のおかげで教団とは距離をとることができた」という。来年には孫ができる予定。
私は地下鉄サリン事件後の1996年にオウムに入信し、アレフ、ひかりの輪と約20年間、信者としての活動を続けてきた。オウムの後継団体は現在、主流派(Aleph=以下アレフ=や山田らの集団)と上祐派(ひかりの輪)に分かれて活動しているが、自身の経験も踏まえ、分裂の経緯とその特徴を明らかにしていきたい。
主流派は、2014年頃から麻原の長男、次男、特に次男を新しい教祖にしようと画策していたが、三女をはじめ一部信者が猛反発し、15年2月に山田美沙子ら約30人(公安調査庁発表)を追放する形で分裂した。当初は三女派と公安当局も見ていたが、当の三女は山田美沙子との関わりを否定。繋がりを示す確固たる証拠も無かったのであろう、「三女派」ではなく、「山田らの集団」と公安調査庁が命名した。山田美沙子はアレフの金沢支部長だったが、支部ごとアレフから切り離されたため、山田らの集団は金沢を拠点に活動していると思われる。
同時期にアレフを辞めた元信者と話す機会があったが、その人によると「(次男は)教祖になれても、グル(霊的指導者)にはなれない」という考えを述べていた。麻原は長男、次男に関して「生まれながらにしての最終解脱者」としていたが、あくまでも自分たちのグルは麻原一人という想いを抱いているのだろうと推察する。
よって、主流派のアレフと山田らの集団の大きな違いは、長男、次男を後継者として受け入れるか受け入れないかという点にある。長男、次男が最終解脱者であるという認識そのものはアレフ、山田らの集団双方が持っていたとしても、麻原の代わりとして受け入れられるのかどうかの判断の違いであろう。双方ともに麻原への絶対的帰依は表見上からも見て取れるし、両者の対立がオウム真理教の一連の事件に関わるものではないことから、事件に対する見解も大きく変わっているとは思えない。
1999年12月に公式見解では弟子たちが関与したことは間違いないとして謝罪表明もしたが、教団内部で統一された意見ではなかった。上祐の出所にあわせて団体規制法を適用しようとしていた時(同法施行は12月27日)、批判をかわすために苦し紛れに表明したものに過ぎなかったのである。
その後、被害者賠償契約を結んだ時に、上祐のコメントが信者に対して出され、私は当時の大阪支部長より説明を受けた。事件は必然であったという無責任極まりない主旨の内容に議論となったのであるが、その時「中山さんは本当に賠償した方が良いと考えているの?」などと聞かれたことがあった。「当たり前じゃないですか」と答えると、「凡夫にお金を渡すことは功徳にはならないんだよ」という返事が返ってきた。あまりにも不謹慎な回答に呆れかえってしまったのだが、主流派の考え方をよく現していると思う。
つまりは、謝罪も賠償も世間の批判をかわすための戦略でしかなかった。その戦略を前面に出して、団体存続理由にしてきたのは上祐派ひかりの輪であった。
99年12月に上祐が広島刑務所を出所するとほぼ同時期に団体規制法が施行された。オウム真理教はアレフと名称変更し、被害者との賠償契約を結んだ。そのことで「賠償を支払うために教団を存続させる」という大義名分を得ることとなった。2002年1月には正式に上祐がアレフ代表に就任した。そして行ったことは、「麻原隠し」である。というより「上祐の教祖化」と言った方がいいかもしれない。上祐派の言い分では、事件を反省し麻原を相対化していく過程であったと説明しているが、団体規制法に対する対策だったという疑念はぬぐい切れない。