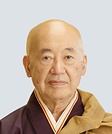失われた念仏のうたごえを求めて(2/2ページ)
浄土宗龍岸寺住職 池口龍法氏
しかしながら、バブルの甘い蜜を吸ったことがない私たちの世代にしてみれば、この日本の経済が豊かになっていくという感覚を味わったことすらない。同時にまた、戦争も戦争の後遺症も知らない宗教的心情を抱くことへのトラウマもない。1995年にオウム真理教が地下鉄サリン事件などを起こしたときは、宗教の持つ力の怖さに日本中が震撼したが、あの事件からもう25年が経つ。宗教を心の軸に生きていくことを提案しやすい土壌は整っている。
この10年ぐらいの出来事を振り返れば、人々の関心は着実に宗教に向いてきている。象徴的だったのは、リーマンショック翌年の2009年に開かれ、100万人近い入場者数を記録した「国宝阿修羅展」(東京国立博物館)であろう。阿修羅像のフィギュアが飛ぶように売れたのは、仏像が「遠くから拝むもの」から「近くで愛でてよいもの」に変わったことを意味した。
雑貨店などの店先にお洒落な朱印帳が並ぶのも、自然な光景になった。お寺にお参りするときには、数珠とあわせて朱印帳を持参するのがひとつのマナーになり始めている。信仰心を持たない若い世代でもファッション感覚で「ご朱印お願いします」と朱印帳を差し出す。お寺や神社も、参拝者に喜んでもらえるように、趣向を凝らした限定朱印を用意する。その善意が仇となり「レア朱印」と書かれてネット上で転売されるのは、現代の朱印文化の闇の部分だが、それほどまでに朱印文化はポップカルチャーになっている。
他にも、お寺の境内でカフェやマルシェを開いたりと、志ある宗教家や宗教関係者たちは、奇策をいとわず手を尽くして宗教への「入り口」を用意してきた。私も09年にフリーペーパー「フリースタイルな僧侶たち」を創刊するなど、「開かれたお寺」をつくるムーブメントには絶えず関わってきた。お寺を取り巻くイメージは、ずいぶん明るくなったと思う。
そこへきてのコロナ禍である。ご朱印やカフェなど、参拝者に楽しくお寺時間を過ごしてもらう手法は突如としてタブーになった。私のお寺でも、頻繁に行っていたライブイベントや企画展示などを今後どうしていくか、見通しは立たない。だが悲観もしていない。なぜなら、日本全体が命の危険にさらされている今、人々は心のよりどころを求めている。これまでは宗教へのユニークな「入り口」が話題を集めてきたが、もっと本質的なもの――念仏、坐禅、法話、法要など――が注目されていくにちがいない。そして、これらの本質的なものこそ、わざわざカフェやライブなどに手間をかけてきた宗教者たちが、目を向けてほしいと願ったものに他ならない。
もちろん、お寺に集まって念仏を唱えるのは、マスクをしたままだと苦しいし、マスクを外すと飛沫が飛び交う。したがって今、日本のお寺が取り組むべき喫緊の課題は、オンライン布教だと思う。念仏のみならず、法要や法話にしても、オンラインで配信すれば、遠方に暮らす檀家さんとコミュニケーションを取れる。これまで縁のなかった人にも教えを伝えられる。機材の購入などに多少の初期費用や慣れるまでの労力が要るとはいえ、教化活動の幅を大きく広げてくれる。コロナ禍の厳しい時期に、オンライン布教にどれだけ注力できたかということは、日本のお寺への評価を大きく左右するだろう。失言が炎上を招く怖さから配信に抵抗感を持つ声も聞くが、人々の苦しみに寄り添ってこそ宗教の価値がある。
海外ではダライ・ラマ法王はじめ、YouTube(ユーチューブ)チャンネルを布教に活用する僧侶は少なくない。動画を見ていて感じるのは、布教への熱量である。日本の現状は動画配信の分野において立ち遅れている。檀家に対して布教することを重んじてきた日本では、広く世界の信者に配信するスタイルが馴染まなかった背景もあるが、そういう事情を差し引いても忸怩たる思いを抱く。冒頭に書いた山本師はじめ、信仰文化を生きがいとして生きてきた人たちなら、YouTubeであれSNS(会員制交流サイト)であれ、使えるツールはとにかく使って宗教を語ってきたはずである。そのような先達の視線を今思い出しながら、「念仏はいのちのうたごえ」という言葉が再び腑に落ちるほどに、この国の宗教文化を深く耕していきたいと願うのである。