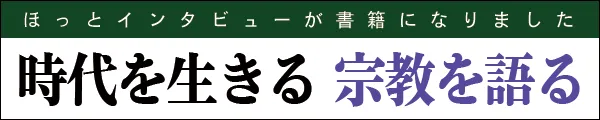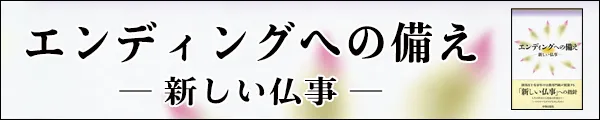正義に殉ずるとは 映画「ボンヘッファー」で(12月3日付)
現代キリスト教にも大きな影響を与えた神学者で、ナチスへの抵抗運動をし、ヒトラー暗殺計画に関わって処刑されたドイツの牧師ディートリヒ・ボンヘッファーを主人公とする米映画「ボンヘッファー」が反響を広げている。
神と人間の関係、倫理や人の信仰、生きざまについて数多くの著述を残した牧師の死後80年の年に公開された本映画は、幼時から終戦直前の刑死まで、時代の様々な状況に対応しながらその思考を深めてゆく彼の生涯をなぞる。
ファシズムに反抗したこんな牧師の存在を広く知らしめる意味で意義深いが「伝記」というには事実と異なる演出が多いという点に加え、一般的に「悪」に対して「正義」の行いはどうあるべきかという点で大きな論議を呼ぶ。
映画で「暴走車にひかれた犠牲者に包帯を巻くだけでなく、運転手からハンドルを奪ってでも車そのものを止める」との趣旨から「罪」である暗殺を受け入れる牧師の描き方が、米国で以前の議事堂襲撃や移民排斥など自分たちの偏った主張のために暴力も厭わない一部の福音派宗教右派、トランプ大統領支持者から熱狂的賛同を集めているというのだ。
「正義」の履き違えも甚だしいが、それは牧師を「孤高の英雄」とも取れるような映画の描き方にもよる。これは、主観的に設定した「極悪非道の敵」、古い西部劇では先住民、戦前戦後は「ナチスドイツ」や「東側」、挙げ句は宇宙人や「ゾンビ」まで動員して、敵を抹殺し尽くす「孤高のヒーロー」が喝采を浴びるステレオタイプのハリウッド映画の流れでもある。
しかし現実の彼は違う。各国を回ってエキュメニカル、そして他宗教との対話にも尽くした国際人であり、研究でも抵抗運動でも幅広い仲間の連帯の輪の中にいた。神を支えとしたそれを自ら「善き力たち」と表現したように、決して「孤独な殉教者」ではなかった。
本作を巡るトークセッションでそれを指摘したボンヘッファー研究者の岡野彩子氏が強調するように、宗教的にさらに重要なのは、葛藤の末に決断した彼が決して人間の基準で自己正当化をせず、罪の責任を負う覚悟を持ち、後はどんな判断を下すかも分からない神に全てを委ねた点だ。
戦争や抑圧が絶えない現代でも、正邪の見極めとそれに基づく行動選択は単純ではない。戦前の日本でも、軍国主義に迎合する教義の意図的な“履き違え”が横行した。宗教者にとってのこの映画の真価は、いかに現実世界を見据え、信仰の深みで真に正しい道を示すかを考えさせるところにあろう。