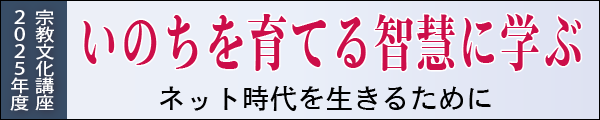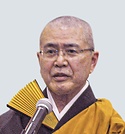ゼロからの新寺建立 「法力」に導かれ僧侶に
大津市 高野山真言宗薬王院 石崎法潤住職

2016年に大津市南部の住宅街の一角に新寺「薬王院」を建立した尼僧。高野山真言宗の被包括寺院となり、今年4月には滋賀県から宗教法人の認証も受けた。「寺院消滅」がささやかれる時代にゼロからの法人設立は珍しい。
寺は家一軒分ほどの区画にあり、薬師瑠璃光如来を祀った本堂と庫裡が立つ。本堂には護摩壇もあり、毎月28日には護摩供法要が営まれる。
得度したのは01年、49歳の時だった。なぜ僧侶になろうと思ったのか――。そう尋ねると「法力」というフレーズを口にし、こんなことを語り始めた。
40歳の時、友人との旅行中に見えるはずのないものが見えた。友人の傍らにおじいさんの影がつきまとっていたのだという。その後しばらくすると、自宅で営む化粧品店のブラインドに黒い仏堂らしきものが映った。
どこからともなく聞こえてきた「奈良の薬師寺に行け」の声に従って、奈良市の法相宗大本山薬師寺を訪れると、ブラインドに映ったものが薬師三尊だったことに気付く。その後数年間は「法力」に怖さを感じ、悶々として過ごしたという。
薬師寺の僧侶に相談すると「人を救う意思があるならば仏の世界でやりなさい。ただし、師を持ちなさい」と諭された。その言葉通り、00年に知人から紹介された北九州市の行者に弟子入り。師から高野山真言宗親王院(和歌山県高野町)の安田弘仁住職(当時)の下で得度するよう勧められた。ここで高野山との縁が生じる。
同院で得度を終えると今度は約5カ月間の四度加行に入り、そこで体験した護摩行に感銘を受けた。それまでは救いを求める信者から一対一で相談を受ける形が基本だったが、護摩供なら護摩木に願いを書いてもらうことで不特定多数の人を救えると感じたからだ。
活動拠点だった滋賀県湖南市の自宅に護摩壇は設置できない。やはり寺が必要と思った矢先、知人の所有地を売ってもらえることになった。ここに建てたのが薬王院だ。
6歳の時に死に別れた父も熱心な行者だった。今は次女の亜衣氏(42)が石崎氏の背中を追って04年に得度。亜衣氏の息子・正賢氏(19)も「祖母は幼い頃から憧れの存在。将来は寺を継ぎたい」と話す。亜衣氏は「母は自身の夫が亡くなり、失意のどん底にいる時でも信者から助けを求められると飛んでいって必死に祈っていた。そんな母を手助けできる存在でいたい」。
(岩本浩太郎)