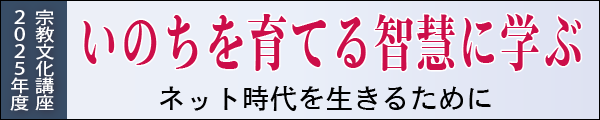飛び地を開墾し菜園に 若者の社会参加を支援
静岡県富士市 浄土宗法源寺

雄大な富士山を本堂越しに拝むことができる浄土宗法源寺(静岡県富士市、髙瀬裕功住職)は、2021年に「農園部」を発足させた。若者支援の一環として始めたものだが、次第にその輪が広がり、地域の人々との交流の場にもなっている。
同寺から徒歩1分の荒れ放題だった飛び地境内を畑として開墾。そこを家庭菜園ならぬ寺庭菜園「青空」と名付け、月に2回ほど活動している。きっかけは髙瀬顕功副住職(41)が、ひきこもりや不登校の当事者・家族を支援する富士市若者相談窓口「ココ☆カラ」から、コロナ禍で若者の就労体験、社会体験の場が減っていると相談されたことだった。
「様々な事情で一般的な就労が難しい人たちに向けて、社会参加の場を用意することも大切」と髙瀬副住職。新規や入れ替わりはあるものの、農園部の主要なメンバーとして5~6人が継続的に参加している。
黒色の農業用マルチシートをかけていなかった畝のジャガイモが生育不良になったり、秋になり周囲の住宅の影が伸びて日照不足になった一画があったりするなど、活動は手探り。「自然を相手にしていると、思い通りにならないことやその逆もある。そうしたことを肌で感じられるのも学びになる」と、試行錯誤しながら作業に取り組んでいる。
畑には現在6本ほどの畝があり、この夏はトマトやズッキーニ、ゴーヤなどを育てた。メンバーで収穫し、余った分はお寺で引き取る。髙瀬副住職が棚経で檀家を巡る際に「よかったらどうぞ」と手渡し、同寺が農業や家庭菜園をやっていると知れると、そこから話が盛り上がることも。また、近所の人から作業中に畑の様子について声を掛けられることも増えてきた。
それでも農園部だけの閉じた人間関係にならないよう、ジャガイモやサツマイモの収穫時には地域の子どもたちに声を掛け、農園部メンバーには指導員役を担ってもらっている。「最初は不慣れで戸惑っていたようだが、子どもたちの喜ぶ様子を見て、そして頼られることで、若者たちもまんざらではないようだった」と振り返る。
収穫したイモは一度本尊に供えた後、おさがりとして子どもたちに配った。「参加した子どもやその親に、お寺を気軽なものとして慣れてもらうため、あえてそうしている。同じ気持ちで農園部のメンバーにも、作業後は毎回、本堂の前で休憩してもらうことにしている」と話す。
(佐藤慎太郎)