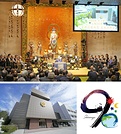祭りのはたらきを再確認 高い次元から苦難の回復力
東京工業大教授 弓山達也氏
「久しぶりだね。また会えたね」「1年ぶり?」といった声が浪江の請戸漁港そばの苕野神社に響いた。昨年も本欄で書いたが、東日本大震災で社殿が流出し、氏子も離散状態の神社の祭礼・安波祭が、再建されて丸1年経った神社境内で行われた。
世間は狭く、昨年も筆者と同じように被災地の祭りの調査をしている研究者数名に会ったが、今年も田植踊りの一人がそうした大学院生だった。また昨年暮れに完成した同神社再建までのドキュメンタリー映画「そこにあるべきものたち」の試写を見逃し、何とか見たいと思っていたら、横に板橋基之監督がいた。
板橋監督は自身のブログ等で、地域の人たちの上を向いて歩く姿、つまり「幸せ」を考えてドキュメンタリーを作るという。何気ない当たり前のような言葉だが、被災地で研究者は不幸に焦点を当てがちで、耳を傾けなければならない一言と思った。実際、筆者も一緒に行った國學院大学の院生たちも、調査というより、浜通りで祭りの手伝いをしてきて、地域の皆さんの元気な姿を見たいと思って安波祭に駆けつけたのだ。
祭りが人々を元気づけることは、宗教研究者なら自明に思えるが、いったいどのような仕組みなのだろうか。スピリチュアルケアの図式を使えば、人生の危機にあって、なぜ生きるのか、なぜ苦しむのかというスピリチュアルな問いが発せられ、ここから自分を超えた大いなるものに従いつつ、生きる意味の探究が始まり、より高い次元での回復に向かうと定式化できよう。しかし宗教無関心層が広がり、ISSPといった国際的な社会調査では神を信じる割合が40カ国中最下位の日本にあって、自分を超えた大いなるものという垂直軸は設定しづらい。
東日本大震災と同様に、コロナ禍も人々に離散、地域の分断、死という悲しみを与えた。その中にあって祭りが人々の新しい視点をもたらしていることが地元の新聞をめくると判る。
例えば浜通りの盆行事であるじゃんがら念仏踊りがオンライン開催になった時、人前では披露できないものの「提供できてよかった」「見てもらえたらうれしい」と離散した他者との再会の期待の声が報じられた。他者への眼差しは先祖にも及び、「大切な人をしっかり供養」との思いがメンバーの背中を押したと、死の悲嘆を乗り越える供養の重要さが伝えられた。先祖への思いは「伝統ある行事は絶やしてはいけない」「古里の象徴」「郷土愛を深める」と、祭りが伝統や郷土愛を目覚めさせ、地域再建の決意に昇華させていることが判る。
ここで語られる先祖、伝統、郷土は、大いなるものの視点を垂直軸とし、他者の視点を水平軸とすると、「斜め上からの視点」とも言えよう。この斜め上からの視点が死、離散、被災という危機に際して、生きる意味の探究を促し、死を悼む供養、離散から再会への期待、被災のダメージから共同体再建の決意といった高い次元での回復をもたらす。だからこそ、祭りは苦難に際して人々を元気づける原動力となる。
なお先の板橋監督作品は一般上映準備中という。ぜひ早く全国公開され、祭りの意味を再確認したい。