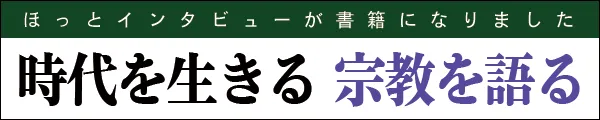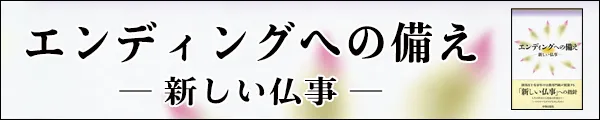がんと向き合い続ける医師・日本対がん協会会長 垣添忠生氏(84)
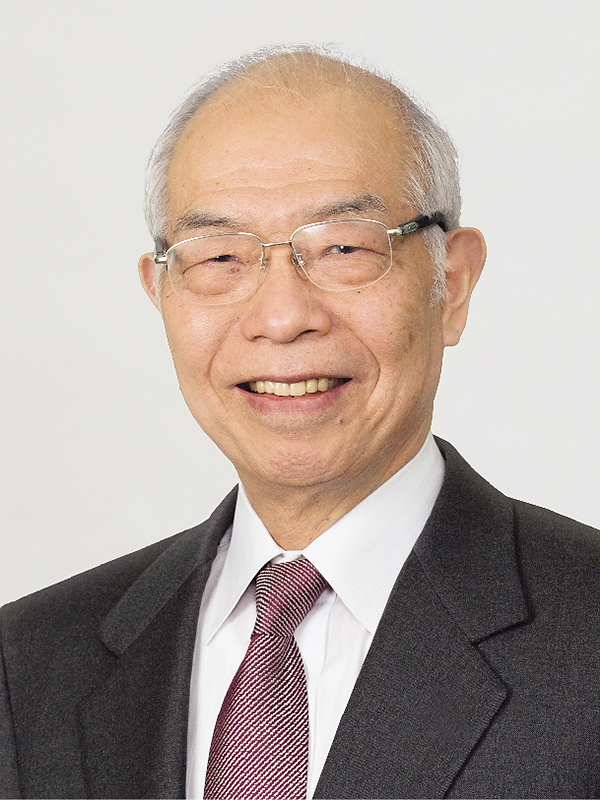
泌尿器科医として日本のがん治療を牽引。国立がん研究センター総長在任中に自身もがんを経験。妻もがんで亡くした。専門医、患者、患者遺族という三つの立場を生かし、がんと向き合う全ての人の支援に尽力する。これまでの活動を通して、人が生きる上で必要なのは「希望」だと確信したと話す。
奥西極
医師としてのこれまでの歩みは。
垣添 母が病弱だったことと、高校時代に飼い犬を亡くしたことがきっかけで医師を志しました。医学部で学ぶ中で、患者さんの病状や家族歴から病気がどこにあるかを突き止める内科診断学の思考過程に興味を持ちました。内科的な思考と、外科的なアプローチが同時にできる泌尿器科に魅力を感じ、102人の同級生の中で私だけが泌尿器科に進みました。
医学部を卒業した後は都立の病院に勤務し、また大学で助手をしながら、昼は臨床、夜は実験と夢中で仕事をしていました。1975年から国立がん研究センターに勤務し、手術部長、病院長、中央病院長などを経て2002年から5年間、総長を務めました。総長として、がん予防とがん検診の普及に向けた取り組みを進めました。退任後、現在まで日本対がん協会の会長をさせていただいています。
私自身、大腸がんと腎臓がんを経験しました。いずれも早期に発見し、すぐに仕事に復帰できました。その経験から、定期的ながん検診による早期発見が大切と考えており、国主導の組織型検診の導入を推進しています。
2007年には奥さまをがんで亡くされました。
垣添 考えられるベストの治療をしましたが、間に合いませんでした。しかし、家で死にたいという最後の願いだけはかなえることができました。家では、手作りのアラの鍋をおいしい、おいしいと言って食べてくれたのですが、年末にかけて意識がもうろうとし、大みそかに昏睡、呼吸困難になりました。午後6時15分に妻が突然、半身を起こして私の手を強く握りました。そのまま心肺停止となり、亡くなりました。
妻が亡くなった直後、私の精神と肉体は最悪の状態でした。ウイスキーや焼酎をロックで飲み、ひたすら泣きました。3カ月ばかりそのようなひどい生活が続いて、さすがにまずいと思い、妻の両親のお墓があるお寺に行きました。ご住職の提案で百か日法要を勤め、そこから少しずつ回復していきました。
体を鍛えたり、散歩をしたり、妻への思いを文章にしたりすることで、次第に元の生活に戻…
つづきは2026年1月14日号をご覧ください