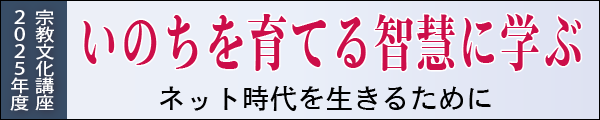AIからの警告 脅威は主体性の喪失にある(11月6日付)
AI(人工知能)の進化に対して、脅威論や肯定論など、様々な論議が交わされてきた。果たして人類は自ら開発した技術によって滅亡の道を歩み始めているのか、それとも新たな可能性への扉を開いたのか。現時点で立ち止まって考えてみると、重要なのはAIの本質を理解することであり、AIの脅威は人間がAIの思考モデルに自己の主体性を委ねてしまうことにあると見えてくる。
今や世界は生成AIの時代に突入した。AI自身が、学習したデータを基に情報を発信する技術を学ぶ。AIは失敗を繰り返しながら、何が正しくて何が間違っているかという基準を学習する。だが、何を教えるかを決めるのは人間であり、人間がどんな価値観を持っているかが重要なポイントになる――とAI研究者の今井翔太氏は述べている。
ドイツの哲学者マルクス・ガブリエル氏は、デジタル化の波にさらされる人間の現状を「私たちが人間でなくなりつつあるのはテクノロジーが人間らしくなっているからではない。テクノロジーを使うことで、人間が人間らしさを失っているからだ」と分析。また、AIが生命体になるのは不可能であり、そのことが人間の脅威とはならないが、人間が非デジタルの現実に費やす時間が減ってしまうことに本質的な問題があると指摘している(「毎日新聞」2023年7月17日付インタビュー)。
ガブリエル氏はさらに「主体的な思考のできないAIによって全てが自動化されることは、人間の進歩の停止を意味する」という。間違いを犯すことのできないAIがチェスや囲碁のゲームに勝ったとしても、それは非人間的で退屈な時間でしかない。人生の意義は、試行錯誤を繰り返しながら成長する内的な進歩にある。思考をAIに委ねてしまうことは、自らの主体性の喪失を意味するものであり、それこそが人類にとって真の脅威だと警告している(『PRESIDENT』24年10月18日号)。
情報学者の西垣通氏は別の観点から提起する。AIを生んだ思想には「超越的な唯一の神が万物を創造したという教え」があり、そこから「人間以外の存在に知性が宿る可能性があるという議論が導かれる」と。いま私たちに求められているのは「創造主が全てを造ったという一神教と、AIのパラダイム(規範となる考え方)を相対化する発想」であり、直線ではなく循環的な世界観、分析だけではなく身体的直観を重んじる仏教などの東洋的な世界観ではないかという。こうした論議は宗教の立場からも深める必要がある。