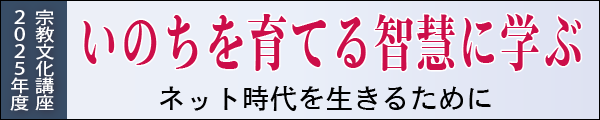平和を語る足元
西本願寺で1月に営まれた御正忌報恩講の親教で大谷光淳門主は今年が戦後80年であることを踏まえ、要旨次のように述べた◆我々の宗門も仏法の名において戦争に様々な形で協力した。戦後はその反省に立った歩みを果たして十分に進めているといえるか。また宗門では戦争だけでなく、差別を肯定し、それを温存・助長するような法話も行われてきた◆大谷門主はその上で、社会に迎合して戦争や差別的政策に協力する愚かさを知る必要性を語り「時代によって変わることのない阿弥陀様の本願による念仏者の生き方を志すこと」を説いた◆本願寺派の関係者にとって特別な内容に感じる人は多くないだろう。しかし、他教団で管長クラスの高僧がこうした発言を公の場ですれば、踏み込んだ話と認識されるのではないか。端的に言って本願寺派でそれが当然視されるのは門主自身に強い問題意識があるだけではなく、宗門が戦争協力や差別に加担してきた歴史を教団として継続的に検証し、啓発してきた経緯があるからだ◆他教団にもそのような取り組みがないわけではないが、少なくとも積極的とは言い難い。組織としての検証や総括の有無は例えば、教団のトップの日頃の発言に大きな差となって表れる。戦後80年の今年、多くの教団は平和への思いを発信するだろうが、それを語る足元は日々問われなくてはならないだろう。(池田圭)