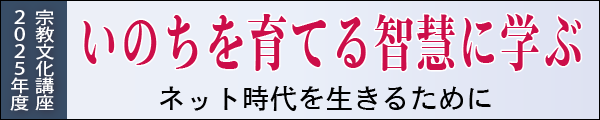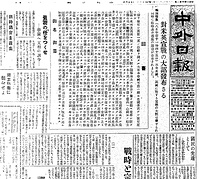ジーヴァカの治癒
厳しかった寒さも和らぎ、急に汗ばむような暖かい日が続いている。免疫機能の低下に加え、飛散する花粉に鼻水が止まらない日々が続く。気候と体調は深い関係にある◆古典には季節の変わり目に体調を崩すことが示され、特に仏教では体質とされる水、火、風など「四大」の不調が病をもたらすとされる。摩訶僧祇律には「病は四百四病あり、風病は百一あり、火病は百一あり……」と規定されるほか、釈尊に帰依したジーヴァカ(耆婆)の話が経典によく現れる◆遊女の子として生まれたジーヴァカはすぐに捨てられた。幼子を見つけたマガダ国の王子が「生きているのか」と尋ねると「生きています(ジーヴァティ)」と答えたのが名前の由来となった。王子に養育されたが、王家の血を引かないため、なりわいとして医学を学び若くして医師になった◆ジーヴァカの存在は教団に少なくない影響を与えたようだ。当時、僧侶は糞掃衣しか着用を認められなかったが、治療の報酬でもらった高価な衣(居士衣)をサンガで使用できるように釈尊に願い出て認められた◆釈尊の吐下を治癒したり、長者の頭蓋骨を切開して虫を取り出したりもした。伝説的な名医であり、彼の手にかかれば現代病である花粉症の治癒もお手の物かもしれない。「まずは四大を整えることから始めなさい」と言われるのがオチかもしれないが……。(赤坂史人)