鎌倉仏教の中世…平雅行著
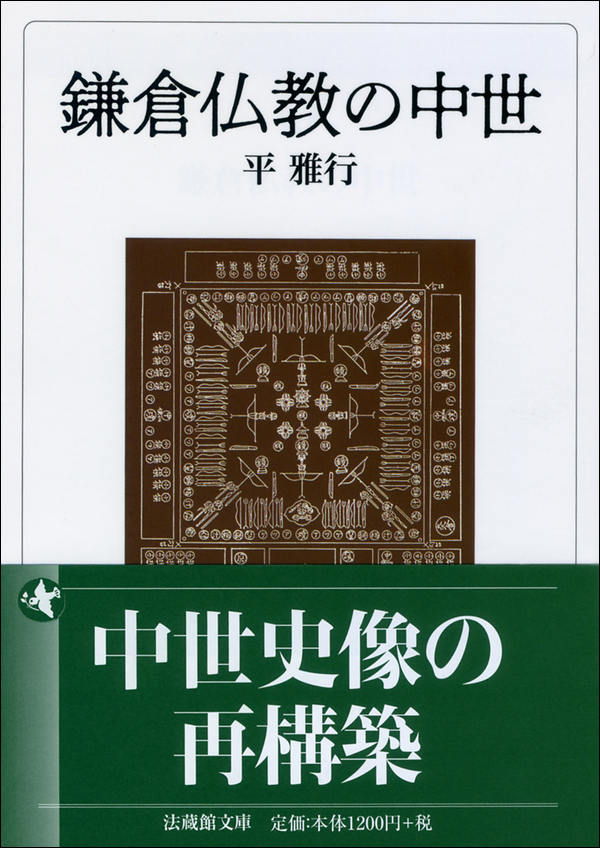
南都仏教・天台宗・真言宗の旧仏教(顕密仏教)の腐敗・堕落に対し、法然・親鸞・道元・日蓮らが提唱した改革運動が民衆に広まり中世仏教の主流になったとする鎌倉新仏教史観は今なお日本人の歴史認識に強い影響を与えている。本書は過去数十年の歴史学研究の動向をベースに鎌倉新仏教史観を強く批判し、鎌倉仏教像の再構築を試みた。
そもそも古典的な中世史像は、中世の始まりを鎌倉時代から院政時代に改めるようになった学説の変化や、旧仏教は中世でも基幹的存在だったとする顕密体制論など、学界では1970年代頃から批判が加えられており、実質的にその歴史像は破綻しているという。
著者は鎌倉時代の仏教改革運動の勃興は旧仏教の堕落ではなく、源平の争乱や承久の乱という日本史上初の全国的内乱で従来の仏教による鎮護国家思想が大きく揺らいだことが要因と指摘する。
本書ではこのほか中世国家の宗教政策や差別を巡る問題、神仏習合、世界史の動きなど多様な観点に論及し、今後の研究課題を含めて日本中世史の全体像をあらためて描き出した。これらの知見には伝統仏教各派の宗学や教団史の見直しを迫る側面もあり、刺激に満ちている。一般向けの書として読みやすい文体でもあり、特に僧侶には必読の一冊だ。
定価1320円、法藏館(電話075・343・0458)刊。


























