「WEターン」を提唱する哲学者 出口康夫さん(61)
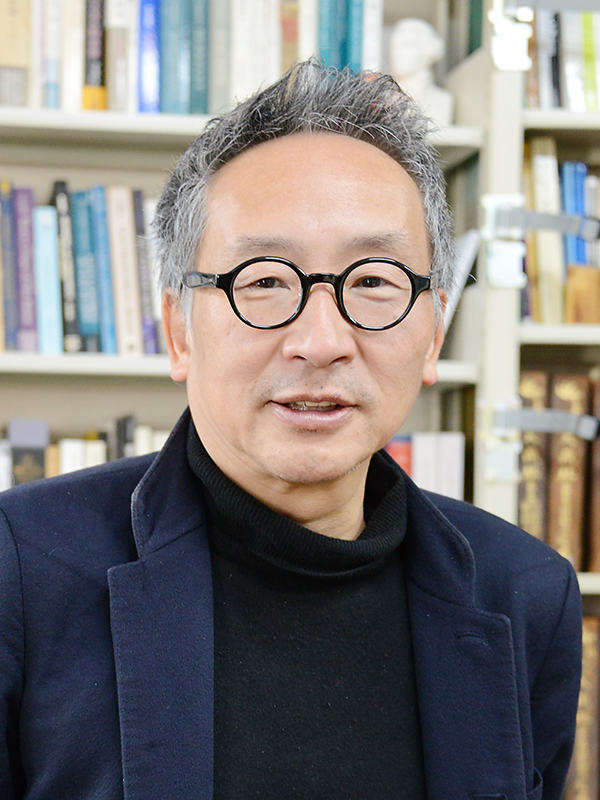
「できること」を基軸にした西洋哲学の人間観に対する新たな立場として「できなさ」に焦点を当てた「WEターン」を提唱する。私単独の行為はあり得ず、全ては「我々(WE)」の行為であり、全体主義的なWEを排した「よいWE」を目指すことで、自然物や人工物とも共生できると訴える。
須藤久貴
「WEターン」とは何ですか。
出口 私個人(I)から私を含む我々(WE)へシフトさせるべきだという哲学的立場、思想として「WEターン」を考えています。その前提で一番重要なものが「できなさ」です。人間というのはいろんな「できなさ」を持っている。鳥のように空を飛べないし、永遠には生きられず、必ず死ぬなどの「できなさ」があります。注目しているのは、一人では何もできないということ(単独行為不可能性)。そういうことを前提に置くことで様々なWEターンが導かれると考えています。
例えばどのような。
出口 身体行為のWEターンでは、誰が話しているか、誰が自転車に乗っているかなど行為者が問題になります。野球をすること、合唱すること――これは一人ではできない。では、一人で素振りするとか独唱するとかはどうでしょうか。一人でできる行為と通常は考えられています。
私は根源的な「できなさ」として、一人ではいかなる行為もできないと考えています。実は単独行為というのはあり得ません。話すとか手を上げるという行為は、体に栄養が入っていないとできないですし、栄養を取るためにはスーパーで食べ物を買う、野菜を栽培する、地球の生態系、空気がないとできない。巨大なシステムがあって初めて「手を上げる」行為が成り立ちます。行為を成り立たせしめているのは、私を一部として含む「マルチエージェントシステム」です(エージェントとは、何らかの力を持ち、それを発揮する存在者のことで、生物や無生物、社会システムなどを含む)。
これまでの通常の見方は、身体行為をしているのは私。従って権利の所有者の単位は我々でなく私という考えで近現代の社会はつくり上げられてきました。WEターンは、従来の法体系とは異なる点が出てきますので、オルタナティブな社会の設計図という面もそこから出てくる。
WE中心になれば、よい社会になるのですか。
出口 社会がWE中心になったとしても、自動的によい社会、ユートピア、理想郷になるわけではありません。
Iに関して「よいI」もいれば「悪…
つづきは2024年3月13日号をご覧ください






























