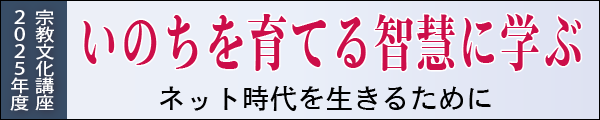おもてなし
京都銀行と京都総研コンサルティングの共催で年頭に行われた「新春経済講演会」で、経済学者の伊藤元重氏が「二〇二五年 日本経済の展望」を語り、脳科学者の茂木健一郎氏が「AI×脳科学からみる近未来」の演題で話した◆伊藤氏は、世界は安定と停滞の時代から変化と不確定性の時代へ向かうと予測。茂木氏は「AIは与えられた規準を最適化するのが得意な究極の優等生」と述べ、客の注文に応じて料理を提供する欧米流の食文化ではなく、亭主が自ら最高の「おもてなし」を演出して提供する日本料理の伝統をAIが学習することは不可能であり、また人間が求める「生きがい」をAIから得ることはできないと論じた◆茂木氏の言う日本流の「おもてなし」を欧米流と比較して言葉にすると、「おもてなしの文化」と「オーダーの文化」の違いとして表現できる。欧米流の「もてなし」は客の求める満足を提供するサービスとして成り立つが、日本流の「おもてなし」は主人が描く最高の心遣いを客のために尽くすことで成立する◆求めに応じてサービスを提供する場合の主体は客であるのに対し、日本流の「おもてなし」は主客の関係は対等である。客が主人に注文を付けることはなく、主人が見返りを求めることもない◆互いにおのれを没した境界に至れば、利害や上下を超えた主客未分の体験を味わうことができる。(形山俊彦)