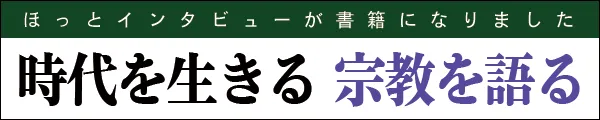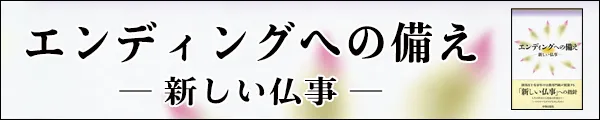遊んで、先生④ 誰もが気安く集まれる場所に

「ともだち診療所」の紫英人院長は、診療所が隣接する真宗大谷派円立寺の次男に生まれた。寺は長男である兄が継ぐ予定だったので「自分は坊さんになる義務さえなかった」。しかしそれで気持ちが自由になる。大学は医学部に入り医療や興味の向いた心理学を学んだが、逆に僧侶になりたいと強く思った。それは、公務員をしながら住職として円立寺を盛り立て「寺は地域のためにある」といろんな働きをしていた父親の順英さん(76)の姿が憧れだったからだ。外科の勤務医をしていて体を壊し内科小児科に転じた後、宗門で教育を受けていた兄が結局寺を出たため、15年前に住職に就任、そして寺の前で開業した。
「ねばならぬではなく、全て好きな道、たまたまのご縁です」。医師と住職の二役と言っても門信徒は近郷に数少なく、葬儀も年に1、2件ある程度。普段は診療所にいることがほとんどなので、寺にいても法事をしても「先生」と呼ばれる。だが地域の人々とは顔見知りで、しょっちゅう寺に話しに来る。
そんな院長住職にとって、医療も寺の仕事も「やはり縁です」という。地区には高齢者も多く、診療は結構忙しい。「医師というのは、その方が病んだときに出会いのきっかけを提供する仕事」。無縁といわれる社会にあっても「人は決して自分一人で生きていけるわけではない。出会いは真宗でも大切にすること。誰もが気安く集まれる公民館のような寺、診療所でありたい」
浄土で皆がひとところに集う「倶会一処」の教え。そこから診療所名を「倶立」と付けた。「友達」に通じるよう仮名で「ともだち」と記された看板には、かわいいイラストがあしらわれている。
来院者は皆、院長が僧侶であることを知っている。あれからランニングが欠かせない習慣になった紫院長は毎日朝夕に町内を走る。道で会う人、田畑で農作業している人に「おはようございます。元気?」と声を掛けると「先生も元気だねえ」と返ってくる。「僕も皆さんに支えられている」。そう感じる院長は話す。「ここだけが診療所ではない。この建物だけが寺じゃない。地域全てが私の働く診療所、寺だと思います」
紫院長が不登校の子どもらに向き合うのは、医師として住職として人々に尽くす生き方の一つの場面であるという。真宗僧侶として「念仏は言葉だけではなく、生活の全て、願いです」と語る。「衣を着ているから念仏ではなく、生きていることが念仏。生きているこの世こそが浄土にならなければいけない」とも。
◇
無縁が無援になるこの社会で、苦難にある人々を支援する数多くの宗教者たちがいる。孤立死に向き合い葬送で人のつながりを支える僧侶たち、地域で生活が困難な人たちに家族代わりとなって伴走する牧師らのNPO、社会のセーフティーネットから落ちこぼれた人々へのシェルターによる寄り添い。今なお差別にさらされるハンセン病元患者たちへの交流、貧困に追いやられた路上生活者や母子家庭への寺院の資源を生かした生活援助。そして、生きづらさで自死を思い詰める念慮者への向き合い。
それらの現場で宗教者たちは「困っている人がいるのを知ったから」「僧侶としてより人間として」「神がせよという通りに働く」と、自らが信ずるところと取り組みとが不可分であることを明かした。その確固たる信仰に裏付けられた現実社会での行いにこそ宗教の輝きがある。
(北村敏泰)
=おわり