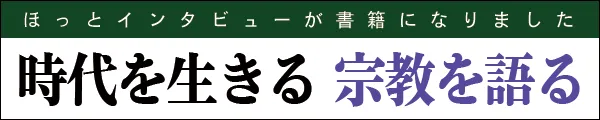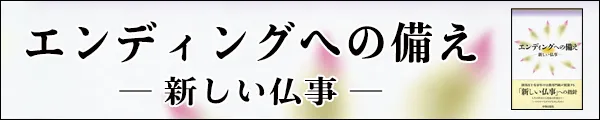加害者家族と被害者家族 オウム教祖の娘から見た社会
京都府立大教授 川瀬貴也氏
先日、「それでも私は Though I'm His Daughter」(長塚洋監督)という映画を見た。この映画は、麻原彰晃こと松本智津夫の三女として生まれた松本麗華さん(以下麗華氏)に関するドキュメントである。
あの事件が起きたとき、彼女は12歳。自分が罪を犯したわけでもないのに、その後の人生を全て「宗教の名の下にテロを行った死刑囚の娘」として生きて来ざるを得なかった。彼女は単に「世間の目が怖い」というレベルを超えて、様々な差別や排除に対峙することとなる。
例えば大学入学が拒否されたり(弁護士の支えで某大学に入学することはできた)、銀行口座を作れなかったり、就職も困難になったり、海外に旅行しようとすると入国拒否をされたり、亡父の遺骨をまともに扱うこともできない(遺骨をめぐって家族間でも争いがあり、国も「どう利用されるか分からない」と遺族に渡すことに反対している)、といった彼女に襲いかかる数々の苦難がこの映画では丁寧に拾われていた(ほぼ6年に及ぶ取材だったそうだ)。
「親の因果が子に報い」という言葉があるが、実質的に社会によって彼女はずっと「連座」させられているわけである。彼女は確かに「加害者家族」の一人ではあるが、明白に社会の被害者でもある。
この映画でも取り上げられているが、麗華氏はある「犯罪被害者」と交流を持ち続けている。その人は原田正治氏という人物で、彼は弟を保険金殺人で殺されたという被害者家族である。
当初、原田氏は犯人(弟の勤め先の人間)に対して激しい怒りを覚え極刑を望むとまで発言していたが、犯人と拘置所で面会を重ねた結果、「死刑にせず、生かして償わせるべき」という考えに変わり、法務大臣に減刑や死刑執行の中止を求めたが、その犯人は死刑を執行される。原田氏はその後も死刑に対する疑問を表明し、孤独を抱える犯罪被害者・加害者の相互交流・支援活動に邁進している。
原田氏と麗華氏の対談はブックレットにもなっており(『被害者家族と加害者家族 死刑をめぐる対話』岩波ブックレット)、映画ではその様子がそのまま使われている。この対談で印象深かったのは、犯罪加害者家族と被害者家族は一見正反対の立場のように見えるが、実は「世間から疎外されている」という点では似ている点がある、と二人が話し合うシーンである。
「事件」の後は、どのようなことをしようとも、その事件と結びつけられてしまい、その結果世間から「まともに扱われなくなる」という点では同じだというのである。原田氏は「加害者家族も被害者」と強調している(原田氏の弟を殺した犯人の姉と息子は自死している)。
このような状況の中、麗華氏は自分のように基本的人権を侵害され、生きづらさを感じている人の支援や相談を行う団体を立ち上げている(一般社団法人「共にいきる」)。我々は犯罪の犯人と被害者にばかり目が行きがちだが、その周りに「被害者」の大きな輪があることをこの映画は教えてくれた。