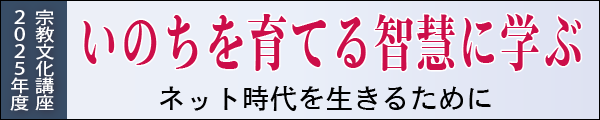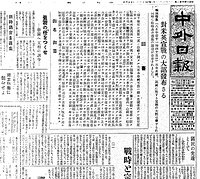ボランティア協力で祭り復活 人とのつながり大切 再認識
大阪大教授 稲場圭信氏
この夏、能登半島地震で被災した各地で復興を願い祭りが執り行われている。春の段階で、今年はとても祭りなどはできないという声を被災地で何度か聞いた。被災地域のある神主さんが、祭りができたらよいけれど、とてもそれどころではない、外からの支援があっても、氏子さん、地域の方々がどう考えるか、と複雑な思いを吐露されていた。その奥能登で祭りが行われている。
甚大な被害で地域住民が広域避難をしており、祭りの執行を断念した地域がある一方で、規模を縮小したり、形式を一部変えたりしながらも祭りを行った地域もある。この暑い夏、様々なキリコ(灯籠)が震災の爪痕が残る被災地を巡行した。
高齢化と過疎化で担い手が不足し、祭りの歴史に幕を閉じることになったにもかかわらず、この地震を機に復活させることになった祭りもある。能登半島地震で甚大な被害をうけた珠洲市馬緤町の「砂取節まつり」だ。揚げ浜式塩田で砂を運ぶ際に歌われた砂取節が、8月13日の祭りの当日、被災地に響き渡り、地元住民に加えて災害ボランティアら約200人が楽しんだという。その砂取節の歌い手5人のうち2人はボランティアで地域と縁ができた人たちだった(毎日新聞、9月5日)。
今、全国各地で祭りや年中行事などの伝統文化の継承に向けた取り組みが進んでいる。背景にあるのは、まさに地方の過疎化や担い手の高齢化だ。企業や住民が連携して担い手不足の解消に取り組んでいる地域がある。福岡県は「住民がきずなを深めるお祭りがなくなると、地域の衰退に直結しかねない」と危機感を募らせ、「地域伝統行事お助け隊」制度を作り、登録したボランティアが派遣要請のあった祭りなどに参加する(日本経済新聞、6月7日)。
担い手だけでなく、祭り自体が変容することもある。夏の行事と言えば、先祖を迎え供養する盂蘭盆会があるが、近年では夏休みの納涼行事としての側面も強くなり、花火大会や盆踊りなどが行われている。かつては、地域全体で盆踊りを開催していたところが多いが、近年では盆踊りを開催する地域が減っており、参加者数が激減している地域もある。一方で、活発化している地域もある。その形態として伝統的な盆踊りが維持されている地域もあれば、若者の間では現代的な音楽やダンスを取り入れたイベントとして行われることもある。伝統的な形式が失われ、風習が廃れていくわけではなく、むしろ新しい形で息吹が吹き込まれている。伝統と革新による日本文化の魅力のひとつと言えるのではないか。
何を守るのか。祭りの形態を守るのか。東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨など災害が発生した各地で、祭りを守った人たちがいる。そして、その実は、祭りが地域の人たちのつながりを守ってきた。大災害をきっかけに、被災地域の人たちと外からのボランティアの交流ができ、新しい祭りの形態ができたところもある。
困難な状況下において地域住民とボランティアの協力によって祭りが復活した事例は、人と人のつながりと伝統行事の大切さを改めて私たちに教えてくれる。