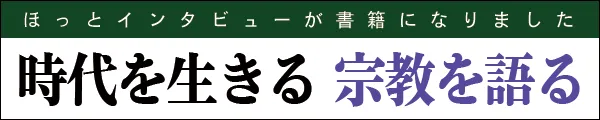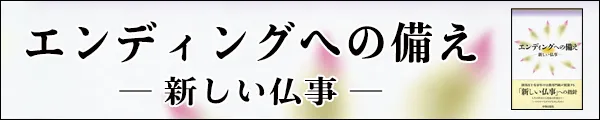再燃させてはならない 国民同士の感情の対立(12月12日付)
前世紀前半のアジア諸国間の戦争と植民地支配は、被害国の「赦し」と加害国の「慎み」が出会った時、初めて和解と共存が可能になるといわれてきた。もとより「慎み」は日本に求められるが、逆に隣国への憎悪をあおる一部の言動によって対立感情を刺激し合う「負」のスパイラルに陥りがちだった。
高市早苗首相の「台湾有事」答弁による対中関係の悪化は軍事衝突さえ危ぶまれる事態になったが、今も底流に潜む歴史認識の隔たりを認識していないと、真の解決策にはたどり着けまい。
世の潮流は、習近平政権の強硬姿勢に反発を強めている。だが、中国との対立が高まれば、中国国民の内政への不満を外に向けたい習政権に「塩を送る」に等しいという識者の指摘がある。政府間の争いに両国民が巻き込まれ、過熱する愚は繰り返したくない。
その視点から、中国の大阪総領事による交流サイト(SNS)への「首を斬る」という投稿にこだわりたい。この文言は日中戦争が始まる2年前の1935年、北京大学教授の胡適が唱えた「日本切腹、中国介錯」論を連想させる。介錯は切腹した武士の首を切り落とす作法である。日本の侵攻を予測の上、中国が3~4年負け続ければ米国とソ連の参戦で日本は自滅し、中国が介錯すると、いささか気のめいる戦略論だった。
胡適は太平洋戦争開戦時に駐米大使を務めていたが、その論は以後の歴史を正確に見通していた。中国は歴史にこだわる国民性と聞く。総領事の投稿は胡適の論を意識しての敵意に満ちた暴言か。ともあれ、その挑発めいたメッセージには冷静な対応が肝要だ。
話を戻すと「台湾有事」を日本の存立危機と関連付ける主張は31年1月、松岡洋右衆院議員の「満蒙は日本の生命線」という国会演説を思い出させる。同年9月、中国侵略が本格化する日本軍の謀略による満州事変が起こり、日中戦争へ突き進んだ。中国は当時のことを歴史教育で熱心に教えるそうだが、日本の歴史教育は近現代史に力を入れない。対立の根の一端は、そこにもあるようだ。日中関係史の知識の乏しさが抵抗感なく「嫌中」感情を引き出し、結果的に権威主義政権を利するという奇妙な構図が浮かぶ。
過去、近隣国との対立は、主にインターネット上などの言論空間で醸成されてきた。感情を刺激する極論がもてはやされるメディア特性により、結果として穏健な中道基盤が掘り崩され、不寛容な社会に変質する。これは中道を説く仏教の本質にも関わる問題である。