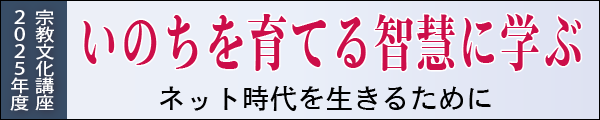無縁墓巡りを主宰する 陸奥賢さん(45)

2011年から大阪市内の無縁墓地やその跡を巡る「大阪七墓巡り復活プロジェクト」を主宰する。江戸時代に行われていた風習「大阪七墓巡り」を追体験するもので、大阪の庶民の「無縁の死者に寄り添うマインド」に成熟した宗教性を感じるという。
池田圭
「大阪七墓巡り復活プロジェクト」とは。
陸奥 大阪七墓巡りは元禄時代には始まっていた大阪の町衆の風習で、お盆に梅田、南浜、葭原、蒲生、小橋、千日、飛田などの墓地を巡拝して無縁仏を供養しました。
実際には遊女と戯れたり、墓地で酒宴をして乱痴気騒ぎをしたり、鐘や太鼓を鳴らしたりとエンターテインメントの要素が強く、町奉行から度々、禁止令が出ています。夜通し行うので肝試しの感覚もあったでしょう。「参加すると性病が治る」という話もあったそうで、清濁併せのむというか、大阪の町の懐の深さを感じます。
発祥の経緯は不明ですが、大坂の陣で犠牲になった豊臣方の死者の慰霊が大っぴらにできなかったので、無縁仏の供養を隠れ蓑に始まったのではないかと推測しています。
復活を試みたのは東日本大震災が起きた11年の8月。大震災で大勢の人が亡くなり、「死とは何か」が社会的な関心事になっていた時期で、僕も死者との関わり方を考え直そうとしていました。
大震災の死者のほとんどは知り合いでも何でもない。そのような死者の人数が連日の報道で積み重なっていく中「無縁の死者を供養する大阪七墓巡りとはどういうことだったのか。無縁の死者との付き合い方を社会実験でやりたい」と自分でも戸惑いながら企画しました。
当時、浄土宗應典院(大阪市天王寺区)のトークイベントで秋田光彦住職や釈徹宗先生(現相愛大学長)からプロジェクトについていろいろ聞かれて、特に秋田住職からは無縁の死者や弱者に寄り添い施し共鳴する実践が最大級の慈悲であるという「無縁大慈悲」という言葉を教えてもらいました。
プロジェクトは現在も続いている。
陸奥 毎年8月13~15日の3日に分け、夕方から夜にかけて巡ります。都市開発で公園になっている所が多く、墓はほとんど残っていませんが、僕がそれぞれの墓地を解説しながら、その名残を伝える地蔵などに花や線香を供えるのが基本です。
初年の参加は30人ほどでしたが、だんだん増えて新型コロナウイルス感染症が流行する前年には約100人に。当初、修験道の人から「そんなことをしたら呪われ…
つづきは2023年12月13日号をご覧ください