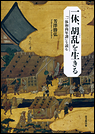国策に振り回され 帰還進まぬ原発事故被災地(5月28日付)
東京電力福島第1原発の事故に見舞われた福島県沿岸部の人口回復が進まない。長期避難によってインフラが破壊された結果、就業先や学校、医療機関や各種商業施設という生活基盤が到底不十分なことで暮らしが元通りにはいかず、帰還する住民がまだまだ少ないのだ。かつての中心街でさえほぼ無人のところが目立つ。
事故前8万8千人だった被災11市町村の人口は今年2月で1万7千人。住民帰還率(人口回復率)は、富岡町16・3%、浪江町10・5%、大熊町7・6%。双葉町に至っては182人しか住んでおらず、たった2・6%だ。遠い避難先での定着などで、元住民にアンケートしても「戻る気はない」がどの町でも多いのは報道の通り。双葉町では復興庁調査でさえ帰還希望はわずか14%である。
それに代わって自治体が力を入れるのが域外からの新たな移住だ。長年全村避難だった飯舘村では1世帯最大500万円もの助成金を出して推進し、花卉農業などを営む移住者の様子も華やかなパンフレットで宣伝している。その結果、同村は人口回復率が25%とずば抜けているが、帰還村民の多くは老人で高齢化率も60%超と突出し、住民票だけで実際には避難先と行き来する人もいる。大熊町では約900人の人口のうち、500人が移住者という。
「本当に先々まで定着してくれるのか」と地元商店主は心配を口にしたが、何より問題は放射能汚染だ。避難指示が解除されても放射線量がまだ高い場所があって被ばくを心配する人もおり、遠方へ避難中の自営業男性は「緊急事態宣言中なのに帰れというのがおかしい。まだ線量が下がっていない所で子供らが学校へ通い、給食を食べている」と指摘。飯舘村の神職は「若い世帯が入ってくるのが本当にいいのか」と疑問を呈する。
同じく今も9千㌶の広大な帰還困難区域が広がる隣接の浪江町津島地区はほぼ誰も住んでいない。津島は、戦前に国策で「満蒙開拓」に駆り出されながら引き揚げ後に行き先がなくなった人々が、やはり国の政策の戦後開拓によって山中の痩せたわずかな土地をあてがわれて入植し、極貧の生活をしながら助け合って農林業を盛り立てた。
人々の強い絆で結ばれた集落には祭りや都会にない自然の豊さがあったが、原発が全てを奪った。「強制避難を苦に割腹自殺した人もいるんだよ」と話す町民の目はうつろだ。原発立地も、事故後の「復興」を旗印とした人口回復もまた国策。「振り回されるのはもうこりごり」との声は当然だ。