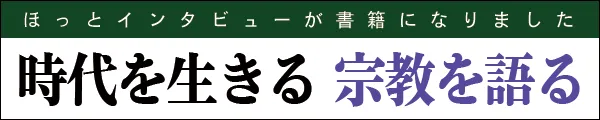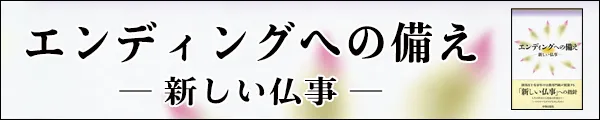災害で問われる この社会の人権感覚(1月9日付)
思い返すと1995年1月の阪神・淡路大震災は、大地動乱の時代を告げる災害だった。また「人の救済を真剣に考えなければ、社会の真の復興はありえないという社会的自覚が生まれた災害」(北原糸子著『災害ジャーナリズムむかし編』)でもあった。
以来、風水害も含め毎年のように新たな被災地が生じるが、被災体験の教訓が生かされない。2024年1月の能登半島地震は復興が著しく遅れ、関連死が既に直接死228人の2倍を超えた。なぜなのか。結局のところ「災害は人権問題」という認識の共有が十分でないことが、大きな要因ではないか。
災害の度に被災した人々が体育館などで雑魚寝する状況は「難民キャンプよりひどく、災害関連死の一因」と、強い批判がある。避難所の生活環境は、国際赤十字などが定めた「スフィア基準」と呼ぶ国際基準で1人当たり専有面積などの最低値が示されている。
24年11月、石破茂首相(当時)が国際基準を満たす努力をすると表明した。避難所の基準は重要だが、注目したのはむしろスフィア基準が掲げる「災害や紛争の影響を受けた人々には尊厳ある生活を営む権利があり、従って支援を受ける権利がある」との基本理念の方だった。阪神・淡路大震災の現場で耳にした「常に救済を求める被災者の役を演じる限り同情は集まるが、公的な支援を求めると敬遠される。日本に住むなら、明日は我が身なのに」という嘆きの声を思い出させた。
基本的人権を基軸に置く日本国憲法は13条、25条で個人の尊重、国による生存権保障義務を定め、国際基準の理念と重なる。肉親の命や家・財産などを失った被災者は、たやすく自立できるものではない。失意に沈む被災者にこそ憲法の人権理念に基づく支援の光を当てなければならない。法治国家なら当然の道理だが、特に高齢者ら災害弱者対策の遅れが指摘される世において、そのことに自覚的であることは大事な意味を持つ。近年、ネットで目につく「被災は自己責任」などという心ない非難に反省を迫ることにもなろう。
被災者の痛みが正しく伝わることが重要な一歩になる。そのために不可欠な、被災地の内と外の間に存在する見えない敷居を払い、情報の風通しを良くする役割を、地域のコミュニティーの拠点であり、災害時の救援活動にも熟達した仏教寺院・教団が担うのがふさわしい。宗派を超えての緊密なネットワークが築ければなお好都合だ。以前から求められていることだが、具体化できないものか。