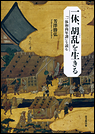周囲との関係性 死の仮想体験での気付き(5月30日付)
自らの最期を仮想体験して「いのち」の意味を考えるワークショップが医療や福祉などケア関係者の集まりで行われた。元々、海外で医療従事者向けに考案されたもので、国内でも宗教者が主催したり大学の授業などでも取り入れられたりしている。がんで重篤になり息を引き取るまでの過程をたどりながら自分の生と死、その在り方を見つめる内容に、参加者は深い学びを得た。
東京で同様のワークショップを実施している僧侶は「死について考え、転じて生を考えることは人間の根源的な問いであり仏教的なアプローチ法でもある」と話す。その自分の「生」が、近しい人々やモノや出来事などによって支えられているということに気付くのが大きな狙いだ。
参加者は4色5枚ずつ計20枚のカードそれぞれに大切にしている物や事柄、思い出や人物などを記入し、この段階で自らが様々な関係性の中にいることを実感する。そしてナレーションで「物語」に入り、自分が病を得て重症化し、ホスピスに入院した末に死を迎えるという“体験”の途上で、カードを少しずつ捨てていく仕組みだ。
「家族」や「仕事」「趣味」など大事なカードは人それぞれ。薄暗く静かな雰囲気の中で物語が進行すると、悩みながら2枚また3枚とカードを丸めて落とすかすかな音がし、末期が近づいて人間関係も希薄な状況になると考えあぐねて手が止まりがちになる人も。最後の1枚を捨てて臨終を告げられる時には、すすり泣きも漏れた。
ここまででも十分に自省的だが、後半の全員での「振り返り」では様々な意見が各人の状況を物語る。カード記入自体が大変で「自分が普段、大事な物事を考えていないと気付いた」。大事な人が周りに多過ぎて「選ぶのがつらかった」。事柄も含めてとても多いのに「モノは全く浮かばず白紙にした」人も。最も話題が集中するのはやはり「最後の1枚」だ。
個別の肉親を挙げる例が多かったが、中年以上では「一番世話が焼け、自分の死後が心配だから」「最も一緒にいる月日が長かったから」との理由で「娘」が目立った。初老の参加者からは「日頃うっとうしく感じているので、すぐに捨てると思ったが、最後はやはり」と「配偶者」が挙げられた。
個々の家族は前段で手放し、最後は「自宅」だったという女性が述べた「自分の魂が家に戻り、そこには家族もいて会えるから」との理由は霊的でもある。仏教でいう「放下」「手放す」が、精神の内奥に迫る術でもあるということが想起される。










![国史より観たる皇室 [附]日本の行くべき道](/article/kanren/books/img/20251128-001@134.png)